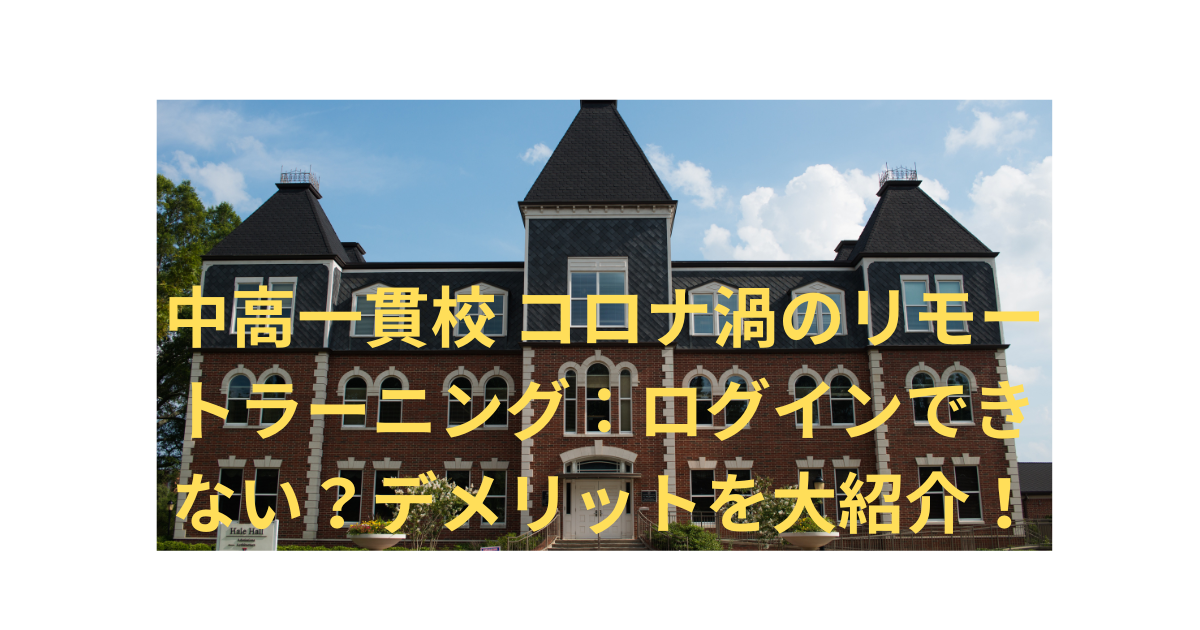
新型コロナの影響でリモートラーニングの学校も多いことと思います。
わが家の息子タンタンの通う、私立中高一貫校でもリモート中心です。
しかし操作に慣れていない中学2年生。
ログインできない、集中しないなど、困ったことが多くないですか?
この記事では、メリットではなく、親目線のリモートラーニング中の困った様子を紹介します。
あるある!わかる!と思ってもらえると思うので、ぜひ最後までお付き合いくださいね。
リモートラーニングの進め方
私立中学で実施しているリモートラーニングの進め方は、どんな感じなのか紹介します。
新型コロナの影響で、どの学校も始業式すら行われず、ただひたすら自宅にこもって過ごしているのではないでしょうか。
息子の中学では、4月上旬に学校から教科書やら課題やらが宅配便で届きました。
そこにはお知らせ系のものも入っていて、クラスメイトや担任の先生が誰なのかを知ることができましたよ。
後日、2便で、課題が届く教科もありました。
美術や音楽、家庭科の課題(教材)が届いたのが印象的です。
ほかには、メールで学習の指示があったり、動画を視聴して、レポートにまとめる課題もあります。
さて、学校からタンタンに与えられたIDで、朝8:30にログインし、毎日が始まります。
クラスの時間割に応じて6時間分(土曜日は4時間)の配信。
家庭科や美術は、実技の道具が郵送されていて、それをやるように指示が出ます。
体育はどうやら先生が体育館で撮ったらしい動画でした。
数学や英語は小テストも配信されていて、ネット上でアンケートに答える気分で取り組んでいます。
リモートラーニングのデメリット
リモートラーニングは良いこともたくさんあると思いますが、いくつかのデメリットがありますよね。
この記事ではデメリットにフォーカスして、わが家の息子が陥った例を、いくつか挙げます。
ぜひ共感してくださいね。
先生によって評価のポイントが違う
先生によっては意地悪な言い方をします。
印象的な意地の悪い先生は、
『この学年は80人しかいないのでしょうか?』
などとオンラインでの提出物が少ないことを、嫌な言い方でメッセージ送信してきたことがあります!
単純に忘れてる人もいるでしょうが、送信したつもりが送れていないことなんて、慣れた大人だってあることですよね。
エラーが出てしまえば、子どもでは対処できないかもしれないし。
なぜそんな言い方をするのか、性格の悪い先生がいるのも事実です。
リモート学習では、授業の様子や、テストを監視することが難しいため、評価方法が変更される場合があることは理解できます。
しかし、なぜお互い苦労して画面に向き合っていることを労えないのか。
このような場合こそ、生徒と教員との交流をメッセージを通してでも良いので、密に行うべきですよね。
「負の発言では子どもは伸びませんよ!」
「逆の言葉で発信して!」
と、心から思いました。
「⚪︎⚪︎人も返信できました、明日はもっと増えているでしょう」とか。
「送信のやり方がわからず困っている人はいませんか?大丈夫ですよ、1度学校に電話して下さい、メッセージでお知らせください」とか。
生徒に寄り添ってくれない不満、不安がぬぐいきれないスタートとなったことは言うまでもないありません。
これから中学受験する方には、そういう日頃の様子をどうにか感じてもらい、学校を選んでもらいたいです。
操作に慣れていない
Z世代とはいえ、リモートラーニングにはテクノロジーの問題が立ちはだかります。
オンライン学習には、インターネット接続やPCの問題、オンラインプラットフォームの問題など、技術的な問題が発生する可能性がありますよね。
これらの問題は、学習プロセスを妨げる可能性がありますが、子ども自身で解決できない場合も多いのではないでしょうか。
さて、息子タンタンは先日、朝8:30のログインに成功し、健康観察などを送信した後、9:00の動画配信を待っている間に認証が切れてしまうトラブルに遭いました。
父母は仕事で不在で、助けは求められません。
パスワードをいくら入力してもログインできず、その日の授業は1つも見ることが出来なかったと、夕方本人から聞かされました。
保険のために母のスマホからもログイン出来る状態にしてあったので、とりあえず課題だけは確認。
そして私も一緒に、一晩いろいろと試しました。
翌朝も同じように試しましたが、タンタンのパソコンからはログイン出来ません。
これはいよいよ学校に電話しようか、とソワソワしていたところ、「もしかしてパスワードの最初の文字が大文字なんじゃない?」ということにようやく気付いたのです!
結果的にそうだったので、もう大丈夫ですが、操作に慣れないタンタンは、リモートラーニング中のテストも大文字小文字や、全角半角の違いでバツ扱いになる、なんて言ってたので、パスワードに大文字小文字の概念があるなんて、恐らく知らなかったことでしょう。
というか、私たちも気付くまでに相当時間がかかりました。
先生も子どもも親も不慣れなことをやっていること。
エラーは度々出ること。
わかって欲しい!
ね、先生!
孤独感との戦い
リモートラーニングは間違いなく、孤独との戦いです。
自己学習が主体となるため、自宅で単独で勉強をしますよね。
このような環境で学ぶことは、まず対話が少ない、教員からのフィードバックも得られない、対面での学習環境で得られるはずの相互作用もない。
嫌なことがあっても友達に休み時間にグチをいうこともできない。
くだらないことを言い合うこともできない。
はっきり言って、つまらない、それに尽きるとおもいます。
誘惑がたくさんある
リモートラーニングは孤独感を存分に味わうとともに、自宅であるがゆえに、誘惑もたくさんあります。
スマホ、漫画、テレビ…。
注意力散漫になりますよね。
気を散らす要因はたくさん。
拍車をかけるのは、授業の進み方が遅いと感じること。
数学は先生が解説プリントを作り、そのプリントも配信してくれていますが、どれほどの役に立っているのか不明です。
作るのに時間はかかっただろう、とは思うけれど、目の前で説明すれば5分で済むかな、という内容。
実際の授業なら、説明後に子どもがノートを取れば十分でしょう。
そういう点で冗長に感じ、PCの画面から目線を外して、手はスマホへ伸びてしまいます。
これは、中学生男子だから、ということではなく、大人でもテレワークあるあるではないでしょうか?
中でも、やっぱり数学は対面授業がいいなぁ、と私は思います。
リモートラーニングでは、集中力を維持することが難しいですもんね。
自分自身を律することができない
今回のリモートラーニングを通して一番腹が立つことは、息子は決定的なまでに自分自身を律することができないことです。
自己管理能力の欠如です。
リモート学習は、時間管理、計画立案、自己管理能力などのスキルが必要。
しかし、息子はこれらのスキルを持たない人です。
授業が配信されるものは、まだマシです。
中には、出席ボタンだけ押して、あとは自習、というものもあります。
たとえば国語は大量のプリント学習。
漢字、読解、調べ学習などですね。
大人の私が見ても、結構めんどいと思われる内容です。
こういうものを息子はためこんでしまう。
50分授業の間に、仕上がる内容ですよ?
それをやらずに、過ごしてしまうわけです。
提出課題だからやらなければならないのに。
本当に腹が立ちます。
説明を聞いて、ガンガン問題を解いて、丸つけして解き直して、またどんどん類題やら発展問題やらやる、そういう中学受験スタイルじゃなきゃダメなんです。
社会科の動画なんて、ぼんやりニュースでも見ているかのようです。
子どもの性格によるでしょうが、タンタンはこういうタイプの勉強は向きませんね。
何度も言います。
皆さん、学校選びは慎重にやってくださいね!
コロナ渦のリモートラーニング ログインできない?デメリットは?:まとめ
さて、リモートラーニングのデメリットについて述べてきましたが、いかがでしたでしょうか?
課題の問題プリント類は郵送されて来ているものもあるし、その場でプリントアウトして使うものもあります。
先日は用紙がなくなり、急いで本人が買いに行きました…。
そんなこともあるので、A4の用紙は多めに用意しておくことをおすすめします。
いずれにしても、何らかの事情があって、学校に通うことができない人以外は、学校へ通うほうがいい、私はそう思います。
クラスメイトと笑い合う、理不尽な思いをする、達成感を一緒に味わう、そういうことって自宅学習では味わえないから。
まだまだ息子には、人との関わりが必要です。
*コロナ渦のリモートラーニングがあっても中間テストは行われました。
